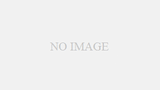こんばんは、Miyu Canvasです。
今日は爽やかな春の一日でした。晴れ時々曇りで、最高気温は20℃ほど。週明けの月曜日ということもあり、朝からエネルギッシュに作業に取り組めました。
前回のブログで少し触れた、Claude 3.7 Sonnetを活用したワイヤーフレーム制作の新プロジェクトが始動して約1ヶ月が経ちました。これまでの経過と、そこから見えてきた「デザイナーとAIの協働」について、自分の頭の整理も兼ねて書き残しておきたいと思います。
AIとの協働プロセスで見えてきたこと
まず、AIツールの強みとして特筆すべきは「アイデア生成のスピード」です。以前は初期のワイヤーフレームを作成するのに丸一日かかっていたものが、AIに的確なプロンプトを与えることで、わずか1〜2時間で複数のバリエーションを生成できるようになりました。時間の節約だけでなく、自分一人では思いつかなかった斬新なレイアウトの提案も得られ、創造の幅が広がっています。
一方で、明確な限界も見えてきました。AIは「なぜそのデザインが効果的なのか」という文脈的理解や、クライアントの事業背景に基づいた深い洞察を持ち合わせていません。そのため、生成されたワイヤーフレームはあくまで「たたき台」として活用し、そこからデザイナーである私が意味づけや最適化を行うというワークフローが定着しつつあります。
最近、テック系ニュースで目にした記事によると、2025年6月28日以降、ヨーロッパ市場で提供される製品・サービスはアクセシビリティ要件への準拠が必須になるそうです。このような法規制の変化も見据えながら、AIツールを活用したデザインプロセスを確立していく必要性を感じています。
変わりゆくデザイナーの役割
興味深いのは、AIとの協働を通じて自分自身のデザイナーとしての役割が少しずつ変化していることです。以前は「グラフィックの作成者」という側面が強かったのに対し、現在は「AIディレクター」や「デザイン戦略家」といった役割にシフトしつつあります。AIに適切な指示を出し、その出力を評価・改善するための専門知識がより重要になっているのです。
最近のデザイントレンドとしても、AIとインタラクティブ技術の融合が注目されていますが、その中でも特に「位置情報を活用した体験設計」の重要性が高まっているようです。ユーザーが今いる場所や状況に合わせたパーソナライズされた体験を提供することが、2025年のUX設計における重要なポイントになるでしょう。
少し話は変わりますが、先週のクライアントミーティングで興味深い議論がありました。あるクライアントが「AIツールが発達した今、デザイナーに高額な報酬を支払う必要性は薄れているのでは?」と率直に質問してきたのです。正直、一瞬ドキッとしましたが、これまでの実績やAIとの協働で生み出した付加価値を具体的に示すことで、むしろ専門家としての価値を再認識していただけたように思います。
フリーランスのUI/UXデザイナーとしての市場価値は、AIの台頭にも関わらず、データ分析やAIインターフェース設計のスキルと組み合わせることで、依然として高い需要があるようです。特に「AIの出力を評価・改善できる目」を持つデザイナーの需要は今後も増加するでしょう。
創造性を維持するための実践
AIツールに依存しすぎると、自分の創造性が鈍るのではないかという懸念も当初はありました。そこで、週に一度は「アナログデー」と銘打って、あえてAIを使わずにスケッチブックと鉛筆だけでアイデアを練る時間を設けています。このオフラインの創造プロセスが、逆説的にAIとの協働をより効果的にしているように感じます。
デジタルデトックスも兼ねて、土曜日には近所の公園でスケッチをする習慣も続けています。先週末は桜も散り始め、若葉の鮮やかな緑が目に染みました。自然からインスピレーションを得ることで、デジタルとアナログのバランスを取りながら、デザイナーとしての感性を磨いています。
明日は午前中にクライアントとのミーティングがあり、このAI活用プロジェクトの中間報告をする予定です。成果と課題を整理し、次のステップへの提案も準備しました。
徐々に形になってきたAIとの協働フレームワークについて、またいずれ詳しく共有できればと思います。
それでは、おやすみなさい🌙