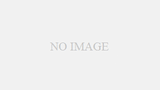こんばんは、はぐみんです。
関東地方も梅雨入りして、雨の日が続いていますね。外遊びが制限される時期ですが、室内での活動がとても充実している毎日を送っています。
梅雨時期の室内活動の工夫
雨の日が続くと、どうしても子どもたちのエネルギーを発散させる場所に悩むものですが、最近は室内活動のレパートリーがとても豊富になりました。
先週から始めた「雨音楽器作り」が大好評で、4歳のAくん(仮名)は「今日はどんな雨の音かな?」と毎朝窓の外を確認するのが日課になっています。空のペットボトルに小豆やお米、ビー玉などを入れて、雨の強さによって音の違いを表現する活動です。
5歳のBちゃん(仮名)は「しとしと雨と、ざあざあ雨と、ぽつぽつ雨で全部音が違うね!」と発見し、3歳のCくん(仮名)は自分で作った楽器を振りながら「雨さん、ありがとう」と優しく話しかけていました。
手作り教材が育む創造力
5月のフリーマーケットで手作りおもちゃワークショップを担当した経験を活かして、最近は園でも手作り教材作りに力を入れています。
今週特に印象的だったのは、牛乳パックを使った「虹色トンネル」作りです。雨上がりに虹が見えることを話していたところ、「虹を作ってみたい!」という子どもたちの声から生まれました。
年中クラスの子どもたちと一緒に、牛乳パックを切って虹の7色に塗り、繋げて大きなトンネルを作りました。Dちゃん(4歳・仮名)は「赤、橙、黄色、緑、青、藍、紫!」と色の順番を覚えて嬉しそうに唱えていましたし、Eくん(4歳・仮名)は「このトンネルを通ると、雨が止んで晴れるかも!」と想像力豊かなことを言ってくれました。
完成した虹色トンネルをくぐる子どもたちの笑顔は本当に輝いていて、手作りならではの温かみと特別感を改めて実感しました。
保育の専門性を高める学び
梅雨の時期は室内活動が中心になるため、保育士としてより専門的な知識やスキルが求められる時期でもあります。最近、特に関心を持って学んでいるのは「感覚統合」の理論です。
雨で外遊びができない時でも、子どもたちの感覚発達をサポートできる活動を工夫しています。例えば、新聞紙をちぎって「雨の音ごっこ」をしたり、タオルを使った「雲の感触遊び」をしたり。
2歳のFちゃん(仮名)は普段は慎重なタイプなのですが、新聞紙遊びでは大胆にビリビリと音を立てて楽しんでいます。触覚刺激が良い効果をもたらしているようで、その後の活動でも積極性が見られるようになりました。
子どもたちの成長を記録する大切さ
保育ICTシステムを活用して、こうした梅雨時期の子どもたちの様子も丁寧に記録しています。室内活動中の子どもたちの発言や表情、作品作りの過程など、小さな変化も見逃さないように心がけています。
3歳のGくん(仮名)は、4月の頃は集団活動への参加が難しい場面もありましたが、最近は手作り教材の活動になると自然と輪の中に入ってきます。「僕も作りたい!」と自分から言えるようになったことを保護者の方にお伝えしたところ、「家でも工作に興味を示すようになりました」と喜んでいただけました。
システムに蓄積された記録を見返すと、子どもたち一人一人の成長の軌跡がよく分かります。これからも一瞬一瞬を大切に記録していきたいと思います。
森探検活動の新たな展開
これまで続けてきた森探検活動も、梅雨時期に合わせて新しいアプローチを試みています。雨の日は実際に森に行くことはできませんが、前回の探検で撮影した写真や、採取してきた葉っぱや木の実を使った室内での「森の記憶」活動を行っています。
年長クラスの子どもたちは、5月に見つけた植物と今の時期の植物の違いを比較しながら、「雨が降ると植物はどうなるかな?」という疑問を持つようになりました。Hちゃん(5歳・仮名)は「雨の日の後の森は、きっと緑がもっと濃くなってるよ」と予想し、Iくん(5歳・仮名)は「虫さんたちは雨の時どこにいるの?」と興味深い質問をしてくれました。
次の晴れ間に森探検に行くのが、今からとても楽しみです。
保護者との連携で広がる学び
最近嬉しいことに、保護者の方から「家でも雨の日の過ごし方を工夫したい」というご相談をいただくことが増えました。フリーマーケットでの経験や、園での手作り教材の取り組みが、ご家庭にも良い影響を与えているようです。
先日は、4歳のJちゃん(仮名)のお母さんから「週末に一緒に雨音楽器を作ってみました。娘がとても喜んで、雨の日が楽しみになったようです」というお話をいただきました。園で学んだことが家庭に持ち帰られ、親子の時間がより豊かになっているのを感じると、保育士としての喜びもひとしおです。
また、年中クラスのKくん(仮名)のお父さんからは、「牛乳パックでいろいろな工作ができることを初めて知りました。息子と一緒に作る時間が新鮮で楽しいです」という感想をいただきました。
梅雨時期の健康管理
雨の日が続くと、子どもたちの体調管理にもいつも以上に気を配る必要があります。湿度が高く、気温の変化も激しいこの時期は、特に注意深く子どもたちの様子を観察しています。
室内活動中心になるため、適度に体を動かす時間も意識的に作っています。「雨雲体操」と名付けた体操では、雲になったつもりでふわふわ動いたり、雨粒になって跳ねたりして、楽しく体を動かしています。
2歳のLちゃん(仮名)は最初は恥ずかしがっていましたが、今では「雨雲体操やりたい!」と自分からリクエストしてくれるようになりました。室内でも十分に体を動かす喜びを感じられているようです。
保育業界の動向への関心
最近、保育業界ではこども家庭庁の予算が大幅に増額されるというニュースが話題になっています。2025年度は7.3兆円という規模で、こども・子育て支援の充実が図られるとのことです。
現場の保育士として、こうした国の取り組みには大きな期待を寄せています。保育の質の向上や、保育士の処遇改善など、様々な面での充実が図られることで、子どもたちにとってより良い保育環境を提供できるようになればと思います。
ただし、大切なのは制度や予算だけでなく、私たち保育士一人一人が日々の実践の中で、子どもたちの最善の利益を考え続けることだと感じています。手作り教材一つ一つに込める思いや、子どもたちとの何気ない会話の積み重ねが、何より大切なのだと思います。
これからの梅雨時期に向けて
6月も下旬に入り、梅雨もこれからが本格的になりそうです。雨の日ならではの発見や学びを、子どもたちと一緒に楽しんでいきたいと思います。
来週は、「紫陽花の色変わり実験」を予定しています。実際の紫陽花の花を使って、pH試験紙のように色が変わる仕組みを子どもたちにも分かりやすく説明できればと準備中です。科学的な興味の芽を育むきっかけになれば嬉しいです。
また、7月上旬には久しぶりに森探検を予定しています。梅雨明け後の森がどのように変化しているか、子どもたちと一緒に観察するのが今から楽しみです。
毎日の小さな幸せ
雨の日が続いても、子どもたちの笑顔は変わりません。むしろ、室内での新しい活動に目を輝かせる姿を見ていると、どんな環境でも子どもたちは学びと成長の機会を見つけ出す力を持っているのだと改めて感動します。
今日も、手作り楽器を振りながら「せんせい、聞いて聞いて!雨の歌作ったよ」と嬉しそうに歌ってくれた3歳のMちゃん(仮名)。その歌詞は「あめあめ ふって ぽつぽつ たのしいね」というシンプルなものでしたが、心の底から楽しんでいる気持ちが伝わってきて、私も思わず一緒に歌ってしまいました。
こうした日々の小さな幸せの積み重ねが、保育士という仕事の醍醐味だと感じています。
明日はどんな発見や成長の瞬間に出会えるでしょうか。雨音を聞きながら、そんなことを考えています。
おやすみなさい🌙✨